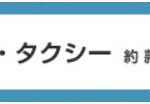今回は「タクシーの帰路高速料金を請求できる?・・・・法律で決まってる?(苦笑)」を書こうと思います。
とりま、タクシーに乗るとき、目的地までのルートによって距離が違って料金が変わることがあります。特に「営業区域から遠く離れた場所に行くと、帰りの高速料金は請求できる」という話をネットで見かけたことはありませんか?・・・・今回は、この情報が本当に法律で決まっているのか、それとも会社独自のルールなのかを現役乗務員目線で見たいと思います。
【ネットでの誤解の正体】
ネット上では、「営業区域から50km以上離れた目的地の場合、帰路の高速料金を法律で請求できる」と書かれていることがあります。
しかし、結論から言うと、法律にそのような規定は存在しません。
ではなぜ、そんな情報が出回るのでしょうか?答えはシンプルです。タクシー会社の独自約款にそう書かれているからです。
例えば、奈良県の「服部タクシー(株)」の約款の第4条に」は次のような条文があります。
「営業区域の境界から概ね50キロメートル以上離れた区域への運送を求められ、運送の引き受けをする場合は、旅客から往復路の有料道路料金に相当する金額を求めることができる。」
これはあくまで会社ルールであり、法律ではありません。・・・それを「法律で決まっている」と発言してしまう人もいるため、誤解が広まっているわけです。
【法律的にはどうか】
道路運送法第13条では「正当な理由がない限り運送を拒絶できない」と定められています。
高速料金の追加請求は運送の拒否ではないため、法的には問題なしです。
タクシー会社が約款で「帰路の高速料金を請求できる」と定めることは可能ですが、国交省の認可を受ける必要があります。
認可なしで運用すると違法になるなります。
【結論】
ネットで言われる「50km以上なら法律で請求できる」は誤解(苦笑)
- 実際には、会社の約款=マイルールで定められているだけ
- 約款に高速料金条項を入れることは、認可を受ければ合法
- 認可なしの運用は違法になる
法律と約款の違いを理解し、情報の出所を確認することが大切の様です。
タクシー会社によってルールは異なるので、「法律」として鵜呑みにせず、あくまで会社の約款上のルールだと理解するのが肝要かも?🤔