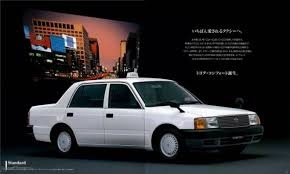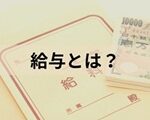今回は「国が『オール歩合は誤り』と認めてから15年・・・それでも変わらないタクシー賃金の現実(苦笑)」を書こうと思います。
とりま、現在主流の完全歩合制ですが、原因の乗務員の方は「あったリ前ジャン」と思っていると思います。
殆どの乗務員の方は、タクシー業界にいると、「歩合給は当たり前」、「オール歩合は合理的」などという言葉を耳にすることがよくあります。・・・知らんけど(笑)
しかし実際には、国の交通政策審議会が平成20年=2008年の答申で、はっきりと「歩合給は必然的でも合理的でもない」と述べていました。
ところが・・・・それから15年以上が経った今でも、現場の賃金制度はほとんど変わっていません。(苦笑)
【答申が示した本当の問題点は?】
この懇題会のメンバーは、タクシー事業者、行政では厚労省、国交省が出席しているので、会議の内容は行政も知っていました。
平成20年12月18日に出された交通政策審議会答申「タクシー事業を巡る諸問題への対策について」には、次のような指摘があった様です。
- 戦後の長い労使協議を経て、固定給主体の「A型賃金」が築かれてきた。
- 規制緩和によってその仕組みは一気に崩され、オール歩合(B型)へと傾いた。
- しかし、それは労働側が望んだものではなく、むしろ強く反対していた。
- 「歩合給はタクシーに必然的、合理的」という決めつけは誤りである。
つまり、国自らが「オール歩合が唯一の正解ではない」と明言していたのです。
規制緩和以前は、固定給を軸にした賃金制度のもとでタクシー事業は立派に機能していた。
答申はその歴史的事実をしっかりと指摘していました。
・・・今では考えられませんが退職金も有った様です。(苦笑)
【それでも歩合が主流のまま】
では現在はどうでしょうか?。
残念ながら、ご存じの様に歩合給主体の仕組みは相変わらず続いています。
首都圏をはじめ多くの会社ではB型賃金の「オール歩合」あるいはAB賃型の「歩合+ボーナス」という形が当たり前になっています」。
固定給を軸としたA型賃金を維持している会社は、全国的にもごく一部に過ぎません。
労働側が長年かけて守ってきた仕組みは崩れ去り、答申で警鐘が鳴らされても、現場の構造は一切変わらなっていません。
結果として乗務員は今なお「売上を上げないと生活できない」リスクを一方的に背負わされ続けています。(苦笑)
【なぜ変わらなかったのか】
背景にはいくつかの事情がある様です。具体的に,は・・・
- 経営側にとって歩合給はコストが変動しやすく、需要減少にも対応しやすい。
- 人口減少や自家用車依存、配車アプリの普及などで需要は縮小傾向、固定給に戻す余裕はない。
- 国交省は運賃規制や車両数の調整には動いたが、賃金制度改革までは踏み込まなかった。
要するに、答申で問題点は共有されたものの、実効的な改革は置き去りにされたままなのです。
【結論・・・動かざること山のごとし(苦笑)】
国の審議会が「オール歩合は誤り」と指摘してから15年、それでもタクシー賃金の実態はほとんど変わらず、歩合主体の仕組みが温存されています。
制度の歴史や現場の慣行を盾に結局ドライバーにリスクを押し付ける構造はそのままです。
答申は記録として残っていても、現実の改善には結びつていません。
結局のところ・・・「オール歩合は合理的」という夢物語は、業界にとって都合が良すぎる口実で、それを放置し続ける行政もまた、タクシー産業の変化の鈍さを象徴していると言えるのではないでしょうか?。