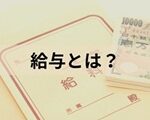今回は「第〇回実証実験?・・・・それもう本格運行ッショ(苦笑)」を書こうと思います。
とりま、いつもの様にパトロールをしていると、千葉県の袖ケ浦でデマンド型乗合送迎サービス が長浦地区での本格運行を開始します、と言う記事をみつけました。この「チョイソコがうら」は令和4年から実証運行が始まり;今迄4回に渡り内容や地域を変えて運行してきた様です。
「地方の交通を救う切り札」として、ここ数年やたらと登場するライドシェアですが、人口減少、バスの減便、タクシー不足等々、そんな現場を見ると、確かに便利で「これなら解決できるのじゃンr?」と期待されます。
始まるたびについて回るのが 「今回は実証実験です」 というお決まりのフレーズで、最初は「な~るほど、試験的にやるんだな」と思いますよネ。
でも終わってみると次は「第2回実証実験を開始します」、さらに「第3回へ」と続くのがデフォルトで、前記した「チョイソコがうら」が令和7年10月 長浦地区での本格運行開始づるのはレアケースです。(苦笑)
利用者からすれば「え? これってもう普通に運行してるんッショ?」と突っ込みたくなるわけで、むしろ実験の看板を外してしまったら、誰も気づかないんじゃないかと思うほどです。
【いつまで実験なんですか?】
確かに実証実験には意味があります。「需要はあるのか?」、「安全に運行できるのか?」を検証するためです。でも、何度も繰り返しているうちに、本来の趣旨よりも 「実験という名札をつけておけば運行を続けられる」 という側面の方が大きくなってきているのが実情でのようです。つまり、実験というより実験ごっこです。
・・・・本格運行にすればいいじゃネ?と思うのはごく自然な疑問です。
【本格運行にできない理由】
それでも「実験」という看板を降ろせないのには、いくつもの壁が有る様で・・・・
・法律の壁
有償で人を運べるのはタクシーとバスに限られるのが日本の制度なのでライドシェアを恒常的に運行する仕組みそのものが現況法的の存在ぢません。なので実験なら「例外措置」として認められるので、結局そこで止まるしかないのが現状です。
・業界の壁
タクシー業界からすれば、ライドシェアは規制緩和で入ってくる競合になるので、今の様に「不公平だ」と強く反発されれば、政治的にも行政的にも手が出せなくなります。(苦笑)
・金銭の壁
実証実験中は国や自治体の補助金が入るので採算が取れますが、しかし本格運行にするとその補助は打ち切られ、事業者が赤字リスクを背負う可能性が有り、だったら実験のまま続けた方が安全なんじゃネ、というわけです。
・安心の壁
住民の中には「知らない人の車に乗るのは不安」、「事故が起きたら誰が責任を取るのか」という声も少なくありません。要は、社会的な合意形成にも時間がかかるため、恒常運行には踏み切れに様です。
【実証実験という都合の良い仕組み
結局のところ「実証実験」という仕組みは、関わる全員にとって都合がいいんです。・事業者にとっては補助金が出るからリスクが少ない・自治体にとっては「地域課題に取り組んでいますヨ」とアピールできる・国にとっては「法律や制度改正せずに様子見」ができる・住民にとっても「とりあえず足が確保される」
等々、つまり、「実証実験」という看板は、誰もが文句を言いにくい魔法の御札なので、だからこそ第〇回実証実験が何度も繰り返されるのです。
【纏めると】
地方ライドシェアが本格運行しないのは、やる気がないからではなく、 制度的にそうするしかない からでBestよりBeterって事の様せす。
むしろ実証実験という名札をぶら下げておけば、補助金も出るし、批判もかわしやすいし、続けやすい、って訳です。
・・・・結果、住民の心の声はこうなります。・・・・・「第〇回実証実験?…それもう本格運行でッショ?」
これはただの実験ではなく、日本式ライドシェア運行モデルのひとつなのかもしれませんネ。・・・・知らんけど(笑)(*´ω`)