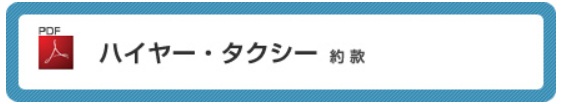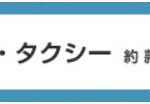今回は「「車内飲食トラブル」・・・・実は約款で拒否できる」を書こうと思います。
とりま、以前ブログにも書きましたが「札幌のラウンジ嬢、タクシー内で飲食トラブル」が未だ話題だそうで(苦笑)、この手の話題、実は定期的にバズります😒
ネットでは「乗務員が細かい」とか「客がマナー悪い」とか、意見はが若手いますが、概乗客が悪い、マナーが無い、一声かけるなどの意見が多い様です。
そもそも、タクシー車内で飲食していいの?禁止なの?・・・という部分、きちんと理解している人は意外と少ない様なので再度、国交省の標準約款を読んでみました。
【飲食禁止の法律はない】
まず大前提として、「タクシー車内で飲食をしてはいけない」という明確な法律の禁止規定はありません。
ですから、缶コーヒーを飲もうが、コンビニおにぎりを食べようが、それだけで即違法というわけではありません。
ただし、ここに一つ重要な視点があります。
それは、車内の秩序を保つ責任は乗務員(運送事業者)にあるということで、車内を汚したり、においが残ったり、他の乗客に不快感を与える行為は、営業上の支障になる可能性があります。
【実は現行の「運送約款」で禁止できる】
ここが今回のポイントで、国土交通省が定めた「タクシー標準運送約款」には、こんな条文があります。
第十三条(運送の拒絶)
乗客が、車内を著しく汚すおそれのある行為をしたときは、運送を拒否することができる。
つまり、「飲食そのもの」を禁止しているわけではないものの、「車内を汚すおそれのある行為」に該当するなら、ドライバーは乗車拒否や降車要請をできるということなので、この「おそれのある行為」が飲食に当たります。要は、現在はその状況に無いが将来的に汚す可能性が有るって事になります。
実際、汁物やアイス、カップ麺などを車内で食べようとした場合、万が一こぼせばシートが汚れ、営業に支障が出るので、この時点で「約款上の拒否理由」として成立します。
【飲み物と食べ物では扱いが違う】
現場では、ほとんどの乗務員が「飲み物くらいならOK」というスタンスです。
しかし、においの強い食品や、液体がこぼれるリスクの高い飲食物はトラブルのもとになり、実務上の線引きが曖昧なため、判断は乗務員個人の裁量に任されているのが現実です。
だからこそ、本来は会社側が運送約款を補足する形で「飲み物は可・食べ物は不可」などの明文化を行えば、現場の判断基準が統一され、トラブル防止につながる様な気がします。
【乗務員が注意しづらい現状】
実際問題として、乗務員が「車内での飲食はご遠慮ください」と言うと、「感じが悪い」、「客に指図するな」とSNSで拡散されるリスクもあります。
そのため、注意したくても言えない、という構図が出来上がっています。😢
こうした背景を踏まえて考えると、車内ステッカーや社内統一ルールで明示するのが最も現実的な様な気がします。
「車内での飲食はご遠慮ください(飲料を除く)」といった表示をするだけでも、ドライバーも乗客もお互いにストレスが減るはずです。
【纏めると】
・法律上は飲食禁止ではない
・しかし、現行の運送約款で「汚すおそれのある行為」として制限可能
・会社が明文化してステッカーなどを車内に貼れば、飲み物と食べ物を区別してルール化できる
結論としては、現場では言いづらいので、ステッカーや掲示が現実的だと思いますが?😊👌